
INDEX
ホームページ作成費用はいくら?この記事でわかること
ホームページを作るときに最も多い疑問が「結局いくらかかるのか」という費用の問題です。
「格安で作れる」と聞くこともあれば、「数十万円は必要」と言われることもあり、情報が多すぎて混乱してしまう方も少なくありません。
実際のところ、ホームページの作成費用は依頼先・目的・ページ数・機能によって大きく変わります。
たとえば、個人のポートフォリオサイトなら数万円で作れることもありますが、企業のコーポレートサイトやECサイトになると、数十万円〜100万円以上かかることもあります。
この記事では、そうした費用の違いを整理し、次のような疑問を解消していきます。
- ホームページの費用相場はどのくらい?
- 制作会社やフリーランスなど、依頼先ごとの違いは?
- 作成費用の内訳や、運用コストには何が含まれるの?
- 費用を抑える方法はある?
この章を読み終えるころには、あなたの目的に合ったホームページ制作の費用感がつかめるようになります。
ホームページ作成費用の相場と目安
ホームページの費用は、誰に依頼するか・どんな目的で作るか・どのくらいの規模にするかで大きく変わります。
同じ「ホームページ制作」でも、個人が数ページのサイトを作る場合と、企業が採用サイトやECサイトを作る場合とでは、必要な工程も金額もまったく異なります。
まずは、依頼先・目的・ページ数という3つの観点から、一般的な費用の相場を整理していきましょう。
この章では、これから制作を検討している方が「自分のケースではいくらかかりそうか」をイメージできるよう、具体的な目安を紹介します。
依頼先別の費用相場(制作会社/フリーランス/自作)
ホームページ制作を外部に依頼する場合、主な選択肢は「制作会社」か「フリーランス」になり、「自作(ホームページ作成ツール)」する方法もあります。
それぞれ特徴や費用の幅が大きく異なるため、まずは全体の目安を把握しておくことが大切です。

制作会社に依頼する場合
制作会社に依頼する場合の費用相場は、30万円〜150万円程度が一般的です。
企業として組織的に制作を行うため、ディレクター・デザイナー・エンジニアなど複数の専門スタッフが関わります。
デザインの品質や構成の提案力、公開後のサポート体制も充実しているのが特徴です。
一方で、打ち合わせや工程管理に時間がかかる分、費用は高めになります。
「会社としてしっかりした印象を与えたい」「採用や問い合わせを増やしたい」といったビジネス目的のホームページには最も向いています。
フリーランスに依頼する場合
フリーランスに依頼する場合の相場は、10万円〜50万円程度が目安です。
個人で対応するため人件費が抑えられ、同じ内容でも制作会社よりコストを下げやすい傾向があります。
小規模事業者や個人事業主のホームページ制作では、フリーランスに依頼するケースも増えています。
ただし、デザイン・コーディング・ライティングなどを1人でこなすため、得意不得意に差がある点には注意が必要です。
また、納品後のサポートや修正対応が限定的な場合もあるため、契約前に保守体制を確認することが重要です。
自分でホームページを作る場合(ホームページ作成ツール)
最近は、専門知識がなくてもホームページを自分で作れるサービスが増えています。
代表的なのは、Wix・ペライチ・WordPressなどのツールです。
費用は月額数千円〜1万円程度で、テンプレートを使えばすぐに公開できます。
初期費用をほとんどかけずに始められるのが大きなメリットです。
ただし、デザインの自由度や機能の拡張には限界があり、本格的な集客サイトやブランドサイトには不向きな場合もあります。
「名刺代わりにとりあえずホームページを持ちたい」「自分で更新して運用したい」という方にはおすすめです。
目的・用途別の費用相場(コーポレート/LP/採用/EC)
ホームページの費用は、何を目的として作るかによって大きく変わります。
会社案内としてのサイトと、ネット販売を行うサイトでは、必要な機能もデザインもまったく違うものになるからです。
ここでは、代表的な4つの目的別に、費用の目安と特徴を紹介します。

コーポレートサイト(企業・店舗の公式サイト)
コーポレートサイトは、会社やお店の情報を伝えるホームページのことです。
会社概要、事業内容、サービス紹介、問い合わせフォームなどが基本構成になります。
費用相場は30万円〜150万円程度。
「信頼感のあるデザイン」や「スマートフォン対応」が重視され、採用情報やお知らせ機能を含むことも多いです。
特に中小企業の場合、ホームページが“会社の顔”になります。
そのため、テンプレートではなくオリジナルデザインを採用する企業が多いです。
LP(ランディングページ)
LPは、特定の商品やサービスを紹介し、購入・問い合わせへつなげる1ページ完結型のサイトです。
費用相場は10万円〜50万円程度。
ページ数が少ない分、全体構成はシンプルですが、デザイン性とコピーライティングの質が成果を大きく左右します。
広告運用(Google広告・SNS広告など)と連携して使われるケースが多く、短期間で効果を出したい場合に向いています。
採用サイト
採用サイトは、求人情報を掲載し、企業の雰囲気や魅力を伝えるためのホームページです。
写真撮影やインタビュー記事など、コンテンツ制作のボリュームが多くなるため、費用相場は50万円〜200万円程度が一般的です。
採用サイトは、応募者が「どんな会社か」「自分に合いそうか」を判断する重要なツールです。
求職者目線のデザインやスマートフォン対応を重視することで、応募率アップにつながります。
ECサイト(ネットショップ)
ECサイトは、商品を販売するための通販サイトのことです。
ショッピングカート機能、在庫管理、決済機能などが必要になるため、最も費用がかかります。
費用相場は50万円〜300万円程度。
WordPressにEC機能を追加するケースから、ShopifyやBASEなどの専用サービスを利用する方法までさまざまです。
販売商品数が多い場合や、独自デザインを求める場合は100万円を超えるケースもあります。
目的別の費用まとめ(目安)
| 用途 | 相場の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| コーポレートサイト | 30万〜150万円 | 信頼性重視。企業・店舗の顔となるサイト |
| LP(ランディングページ) | 10万〜50万円 | 広告連携・1ページ完結型 |
| 採用サイト | 50万〜200万円 | コンテンツ量が多く、写真・インタビュー制作を含む |
| ECサイト | 50万〜300万円 | 決済・在庫管理など機能が多く高額になりやすい |
このように、ホームページの費用は「どんな目的で作るか」によって大きく変わります。
自社が求める成果(集客・信頼性・採用・販売など)を明確にしておくことで、無駄なコストをかけずに効果的なサイト制作ができます。
規模・ページ数別の費用相場
ホームページの費用は、ページ数や規模が増えるほど高くなるのが一般的です。
数ページの簡単な紹介サイトと、10ページ以上ある本格的な企業サイトでは、必要なデザイン・構成・作業量が大きく異なるためです。
ここでは、代表的な3つの規模に分けて、相場の目安を紹介します。
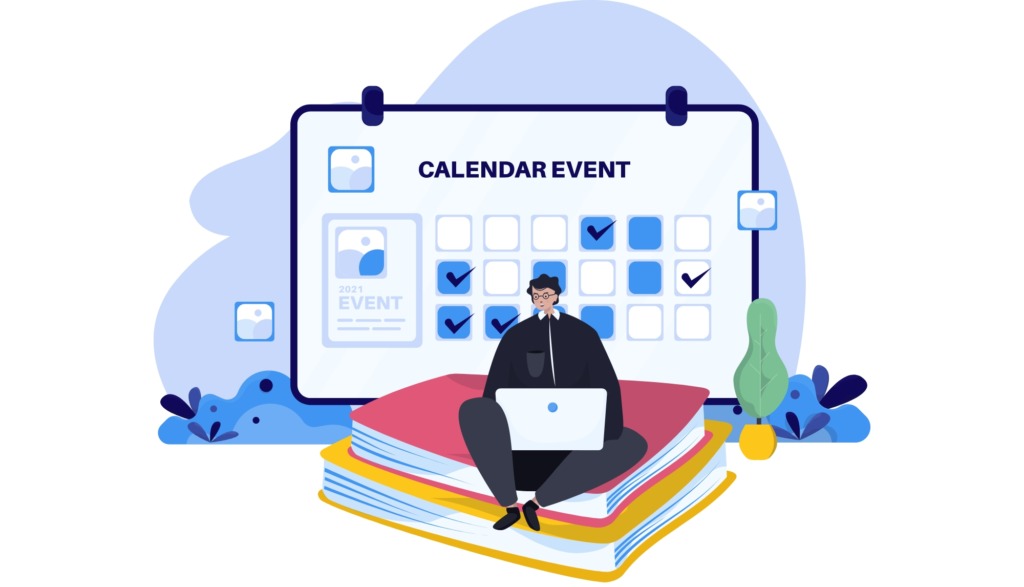
小規模サイト(1〜5ページ)
個人事業主や小さなお店が「とりあえずホームページを持ちたい」という場合によく選ばれる規模です。
トップページ・サービス紹介・プロフィール・お問い合わせフォームなど、最低限の構成で作成します。
費用の目安は10万円〜30万円程度。
テンプレートを活用すればさらに安く抑えることもできます。
ただし、情報量が少ないと検索エンジンからの評価を得にくいため、ブログ機能をつけて情報発信を続けるのがおすすめです。
中規模サイト(5〜15ページ)
中小企業のコーポレートサイトに最も多い規模です。
トップページのほか、会社概要・事業内容・サービス紹介・採用情報・お問い合わせフォームなどを含みます。
費用相場は30万円〜100万円程度。
ページ数が増える分、デザインの統一感や導線設計(見やすいナビゲーション設計)が重要になります。
この規模になると、プロの制作会社やフリーランスに依頼して、デザインと構成をしっかり固めるケースが一般的です。
大規模サイト(15ページ以上)
複数の事業を展開している企業や、採用・EC・ニュース更新などを兼ね備えたサイトがこの規模にあたります。
費用の目安は100万円〜300万円以上。
コンテンツ量が多く、システム構築やSEO対策を組み合わせる場合も多いため、制作期間も長くなります。
ページ数だけでなく、コンテンツ制作(写真撮影・ライティングなど)にかかる費用も考慮が必要です。
規模別の費用まとめ(目安)
| サイト規模 | ページ数の目安 | 費用相場 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 小規模サイト | 1〜5ページ | 10万〜30万円 | 名刺代わり・シンプル構成 |
| 中規模サイト | 5〜15ページ | 30万〜100万円 | 中小企業に多い標準構成 |
| 大規模サイト | 15ページ以上 | 100万〜300万円 | 機能追加・SEO強化・更新機能など |
ホームページの費用を考えるときは、「ページ数×目的」で見積もりを立てるのがポイントです。
必要以上にページを増やしても成果にはつながりません。
まずは「何を伝えたいか」「どんな行動を促したいか」を整理してから、最適な規模を決めるとよいでしょう。
ホームページ作成費用の内訳とは?
見積もりを見たときに「デザイン費」「ディレクション費」「コーディング費」など、聞き慣れない言葉が並んでいて戸惑った経験はありませんか?
ホームページ制作では、ひとつのサイトを完成させるために複数の専門作業が関わっています。
ここでは、主な費用項目とその内容をわかりやすく解説します。
企画・構成費(ディレクション費)
相場:5万円〜20万円程度
制作の最初に行う「目的の整理」「ターゲット設定」「サイト構成(ページ設計)」などの作業費です。
たとえば「どんなお客様に見てほしいか」「どんな情報を載せるか」といった部分を一緒に決めていきます。
この工程をしっかり行うことで、完成後に「思っていた内容と違う」といったズレを防げます。
制作会社では、ディレクターと呼ばれる担当者がこの部分をまとめます。
デザイン費
相場:10万円〜50万円程度
ホームページの見た目を作る工程です。
トップページのデザインや下層ページのレイアウトを作成し、企業や店舗のイメージに合わせた雰囲気を形にします。
「テンプレートを使うか」「オリジナルで作るか」で費用が大きく変わります。
オリジナルデザインの場合、打ち合わせや修正回数も増えるため、テンプレートデザインの採用より費用は高くなる傾向があります。
コーディング費(HTML/CSSなど)
相場:5万円〜30万円程度
デザインデータを実際にブラウザで表示できる形にする工程です。
「HTML」「CSS」「JavaScript」といった言語を使い、ページを動く状態にします。
たとえば「お問い合わせフォームが開く」「ボタンを押すと動く」といった部分はこの工程で実装されます。
シンプルな構成であれば低コストで済みますが、アニメーションや動きのあるサイトにすると費用が上がります。
CMS構築費(WordPressなど)
相場:5万円〜30万円程度
CMSとは「コンテンツ管理システム(Content Management System)」の略で、専門知識がなくても更新ができる仕組みのことです。
代表的なCMSが「WordPress(ワードプレス)」です。 ブログ投稿やお知らせ更新など、自社で情報発信をしていきたい場合に導入されます。
ただし、CMSを入れると制作工程が増えるため、静的サイトよりも費用がやや高くなります。
ここまでが制作の「メイン工程」です。
次は、実際にサイトを公開・運用するために必要な追加費用(写真・文章・ドメインなど)について説明していきます。
この部分を見落とすと、予算オーバーになったり、完成後の運用で追加費用が発生したりすることもあります。
ここでは、実際の見積もりに含まれることの多い項目を紹介します。
写真撮影・素材費
相場:1万円〜10万円程度(撮影ありの場合は10万円以上)
ホームページに掲載する写真をどのように用意するかによって、費用が変わります。
既存の写真素材サイトを使う場合は1枚数百円〜数千円で購入できますが、
自社商品・店舗・スタッフを撮影する場合は、プロカメラマンの撮影費用がかかります。
写真の品質はサイト全体の印象に大きく影響するため、
特に企業サイトでは「撮影に投資する価値がある」と言われています。
原稿・ライティング費
相場:1ページあたり1万円〜5万円程度
「会社紹介」「サービス内容」「代表あいさつ」など、文章をライターに依頼する場合の費用です。
多くの制作会社では、依頼主が原稿を用意する前提になっていますが、
文章作成を任せたい場合は別途費用が発生します。
検索で上位表示を狙うなら、SEOを意識したライティングが重要です。
専門ライターに依頼することで、より成果につながるホームページになります。
ドメイン・サーバー費
相場:年間1万円前後(ドメイン+サーバー)
ホームページを公開するには、住所の役割をもつ「ドメイン」と、データを保存する「サーバー」が必要です。
例えるなら、ドメインは「住所」、サーバーは「土地」のようなものです。
・ドメイン(例:example.com)…年間1,000円〜3,000円程度
・サーバー …年間6,000円〜12,000円程度
多くの制作会社では初年度の契約代行を行い、2年目以降は更新費を自社で支払う仕組みになっています。
SSL対応費(セキュリティ設定)
相場:無料〜数万円
SSLとは、通信を暗号化して情報を守る仕組みのことです。
URLが「https://〜」で始まるサイトがSSL対応済みです。
最近では、GoogleもSSLを導入していないサイトを評価しにくくしているため、
セキュリティ対策とSEO対策の両面で必須といえます。
レンタルサーバーによっては無料で利用できるケースもあります。
テスト・修正・納品費
相場:制作費内(無料)〜数万円程度
ホームページの動作確認や、公開前の微調整にかかる費用です。
ページの表示崩れやフォームの不具合などを確認し、修正してから納品します。
特にスマートフォン対応(レスポンシブ対応)を含む場合は、
複数端末での動作チェックが必要になるため、この工程が重要です。
費用内訳まとめ(目安)
| 項目 | 相場の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 企画・構成 | 5万〜20万円 | ヒアリング、構成案作成、進行管理など全体の企画・設計業務 |
| デザイン | 10万〜50万円 | 見た目であるデザインの作成 |
| コーディング | 5万〜30万円 | サイトで表示できるようにし、ページが動く状態に実装 |
| CMS構築 | 5万〜30万円 | 投稿機能、カテゴリ設定などの更新機能の追加 |
| 写真・素材 | 1万〜10万円 | カメラマンによる撮影・素材画像の購入 |
| ライティング | 1万〜5万円/P | サイトに掲載する文章の原稿作成・SEO対応 |
| ドメイン・サーバー | 年1万円前後 | 公開に必要な環境 |
| SSL対応 | 無料〜数万円 | セキュリティ設定 |
| テスト・納品 | 無料〜数万円 | 公開前の最終調整 |
このように、ホームページ制作費の中には「見えにくいけれど重要な項目」が多く含まれています。
見積もりを比較する際は、単に金額だけでなく、どこまでの作業が含まれているかを確認することが大切です。
ホームページ運用・保守にかかるランニングコスト
ホームページは、作って終わりではありません。
公開後も安定的に運用していくためには、サーバー費・ドメイン費、更新費、セキュリティ費用など、継続的なコストが発生します。
このランニングコストを正しく把握しておくことで、予算の計画が立てやすくなり、後から「こんなにかかると思わなかった」といったトラブルを防げます。
ここでは、主な運用・保守費用の項目を紹介します。
ドメイン・サーバー更新費
相場:年間1万円前後(ドメイン約1,000円〜3,000円/サーバー約6,000円〜12,000円)
ホームページを継続して公開するためには、ドメイン(インターネット上の住所)とサーバー(データの保管場所)の契約を更新する必要があります。
この2つは、ホームページを維持するための最低限の固定費です。
制作会社に保守を任せる場合は、これらの更新費が保守費用に含まれていることもあります。
自社で契約している場合は、契約更新の時期を忘れないよう注意が必要です。
更新・修正費
相場:月額5,000円〜3万円程度(都度依頼の場合は1回5,000円〜)
ホームページに新しい情報を掲載したり、文章や画像を差し替えたりする際の費用です。
自分で更新できる仕組み(WordPressなど)を導入していればコストを抑えられますが、
操作が難しい場合や時間が取れない場合は、制作会社に更新代行を依頼するのが一般的です。
定期的に情報を更新することで、検索エンジンからの評価も上がりやすくなります。
放置してしまうと古い情報が残り、信頼性が下がる原因にもなるため注意が必要です。
保守・セキュリティ対応費
相場:月額5,000円〜2万円程度
ホームページの安全性を保つための費用です。
WordPressなどのCMSを使用している場合、システムの更新やプラグインの管理を怠ると、
サイトが壊れたり、不正アクセスされるリスクが高まります。
保守契約を結ぶと、定期的なバックアップ・ウイルスチェック・エラー対応などを代行してもらえます。
特に会社の公式サイトや顧客情報を扱うサイトでは、セキュリティ対策は必須です。
SEO対策費
相場:月額3万円〜20万円程度(外部委託の場合)
SEOとは「Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)」の略で、
Googleなどの検索結果で上位に表示されるようにする取り組みです。
SEO対策には、以下のような作業が含まれます。
- コンテンツ(記事・ブログ)の作成・更新
- キーワード分析
- 内部リンク・構造の最適化
- 表示速度やモバイル対応の改善
自社でできる部分もありますが、競合が多い業界では専門会社に依頼するケースも多いです。
ただし、短期間で成果を出すのは難しいため、長期的な視点で取り組むことが大切です。
Web広告運用費
相場:広告費+運用代行費(月額5万円〜数十万円)
Google広告・SNS広告(Instagram、Facebookなど)を活用すると、短期間でアクセスを増やすことができます。
広告費用は「クリックされた分だけ支払う(クリック課金制)」が一般的です。
たとえば、1クリック100円・1,000クリックで10万円の広告費になります。
加えて、広告設定や分析を代行してもらう場合は、運用代行費(広告費の20〜30%程度)がかかります。
広告は費用対効果のコントロールがしやすい一方、設定を誤ると無駄な出費につながるため、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。
アクセス解析・改善サポート費
相場:月額1万円〜5万円程度
Googleアナリティクスやサーチコンソールを使って、アクセス数やユーザー行動を分析し、改善点を見つけるサポート費用です。
アクセス解析を継続的に行うことで、
「どのページがよく見られているか」「どんな検索キーワードで訪問されているか」が分かります。
これにより、集客の弱点を見つけ、サイトをより成果の出る形に育てていくことができます。
SNS運用・コンテンツ制作費
相場:月額2万円〜10万円程度
ホームページとSNSを連携させて発信力を高める方法も一般的です。
InstagramやX(旧Twitter)などで日常的に情報を発信することで、認知拡大やファンづくりにつながります。
SNS運用を代行するサービスでは、投稿内容の企画・画像作成・コメント対応などを一括でサポートしてくれます。
特に、店舗や地域密着型のビジネスでは、SNS×ホームページの連携が集客のカギになります。
集客関連費まとめ(目安)
| 費用項目 | 相場の目安 | 主な内容 |
|---|---|---|
| ドメイン・サーバー更新費 | 年間 約1万円前後 | ホームページの維持に必要な基本契約 |
| 更新・修正費 | 月5,000円〜3万円(都度5,000円〜) | 文章・画像の変更、最新情報の追加など |
| 保守・セキュリティ対応費 | 月5,000円〜2万円 | バックアップ・CMS更新・エラー修正など |
| SEO対策費 | 月3万円〜20万円 | 検索順位改善、コンテンツ最適化 |
| Web広告運用費 | 広告費+代行費(月5万円〜数十万円) | Google広告・SNS広告の出稿と運用 |
| アクセス解析・改善費 | 月1万円〜5万円 | アクセスデータの分析・改善提案 |
| SNS運用・コンテンツ制作費 | 月2万円〜10万円 | 投稿企画・デザイン制作・発信支援 |
ホームページの運用費は、「維持するためのコスト」と「成果を上げるための投資」に分かれます。
最初は最低限の保守から始め、反応を見ながら少しずつ集客施策を追加していくのが現実的です。
ホームページ作成費用が高くなるケースと抑える方法
ホームページの費用は、同じページ数でも依頼内容によって大きく変わります。
「思っていたより高い」と感じるケースの多くは、機能やデザインに特別な要件が含まれているためです。
ここでは、費用が高くなりやすい代表的なケースを紹介します。

ホームページ作成費用が高くなるケース
機能が複雑・カスタマイズが多い
見積もりを押し上げる要因の中でも、最も影響が大きいのが「機能面」です。
たとえば、以下のような要件は費用が高くなりやすいです。
- 会員登録・ログイン機能
- 商品の注文・決済機能(ECサイト)
- 予約・スケジュール管理機能
- 多言語対応(日本語・英語・中国語など)
- 外部システムとの連携(顧客管理・在庫管理など)
こうした機能は、一般的な企業サイトには不要な場合もあります。
目的を整理し、「今すぐ必要な機能」と「将来的に追加すればよい機能」を分けることで、初期費用を大きく抑えることができます。
写真・動画・素材をすべて外注する
写真撮影や動画制作をすべてプロに依頼すると、費用が一気に上がります。
特に、モデル撮影や店舗紹介動画などを制作すると、1回の撮影で10万〜30万円以上になることも珍しくありません。
もちろん、クオリティを高めるうえで効果的な投資ですが、
たとえば以下のような工夫でコストを抑えることも可能です。
- 既存の写真素材サイトを活用する
- スマートフォンで自然光を使って撮影する
- 動画は後から短いPRムービーとして追加する
「最初から全て完璧を目指さない」ことが、コストを無理なくコントロールするコツです。
ページ数が多すぎる
ページ数が増えるほど、デザイン・コーディング・文章作成の工数が増えるため、費用は比例して上がります。
特に、採用ページや事業紹介ページを細かく分けすぎると、構成が複雑になり、管理も難しくなります。
最初は「必要最低限のページ」で構成し、
運用しながらコンテンツを追加していく形がおすすめです。
このように、“最初からすべて詰め込まない”ことが、コストを抑える最大のポイントです。
ホームページ作成費用を抑える方法
ホームページ制作の費用は、工夫次第で大きく変わります。
「安さだけを重視する」のではなく、必要な部分にしっかり投資し、優先度の低い部分を削ることが大切です。
ここでは、コストを抑えながら効果的なサイトを作るための具体的な方法を紹介します。
機能を段階的に導入する
最初からすべての機能を詰め込むと、初期費用が高くなります。
まずは「最低限必要な機能」で公開し、反応を見ながら後から追加していく方法がおすすめです。
たとえば、
- 初期段階では「お問い合わせフォーム」だけ
- 集客が軌道に乗ったら「予約機能」や「会員制ページ」を追加
このように段階的に進めることで、初期費用を半分以下に抑えるケースもあります。
テンプレートや既存テーマを活用する
WordPressなどのCMSには、無料・有料のテンプレートが数多く存在します。
デザインをゼロから作るよりも作業工数が減るため、費用を大幅に抑えられます。
最近のテンプレートはデザイン性も高く、スマートフォン対応も標準で備わっています。
「オリジナル性」よりも「コストとスピード」を重視する場合に最適です。
自社で準備できる素材を活用する
写真・文章・会社ロゴなど、自社で用意できる素材が多いほど、制作費は下がります。
たとえば以下のような工夫が有効です。
- スタッフ写真を自社で撮影する
- サービス紹介文を自社で下書きする
- 既存のパンフレットやチラシの内容を再利用する
ライターやカメラマンに依頼する部分を減らすことで、数万円〜十万円単位の削減につながります。
制作範囲を明確にして見積もりを比較する
制作会社やフリーランスに依頼する際は、必ず「どこまでが含まれているか」を確認しましょう。
見積もり内容があいまいなままだと、後から追加料金が発生しやすくなります。
複数社に見積もりを依頼すると、費用相場と作業範囲の違いが見えてきます。
ただし、単に安いだけではなく、サポート体制や実績もしっかり比較することが大切です。
長期的な運用を見据えて考える
「初期費用が安い=総額も安い」とは限りません。
格安制作サービスの中には、月額費用が高く設定されていたり、解約時にデータがもらえないケースもあります。
一時的な安さよりも、3年・5年のトータルコストで判断する方が、結果的にコスパの良い選択になります。
無理に「安くする」よりも、目的に合った費用配分をすることが成功のカギです。
どんなに立派なサイトでも、運用や更新が続かなければ意味がありません。
限られた予算の中で「費用対効果の高いサイト」を目指しましょう。
初期費用0円のホームページ制作サービスは本当にお得?仕組みと注意点
最近、「初期費用0円」「月額○○円だけでホームページが作れる」といったサービスをよく見かけます。
一見するととてもお得に感じますが、仕組みを理解せずに契約すると、長期的には割高になる場合もあります。
ここでは、初期費用0円サービスの仕組みと、利用する際に知っておきたい注意点を解説します。
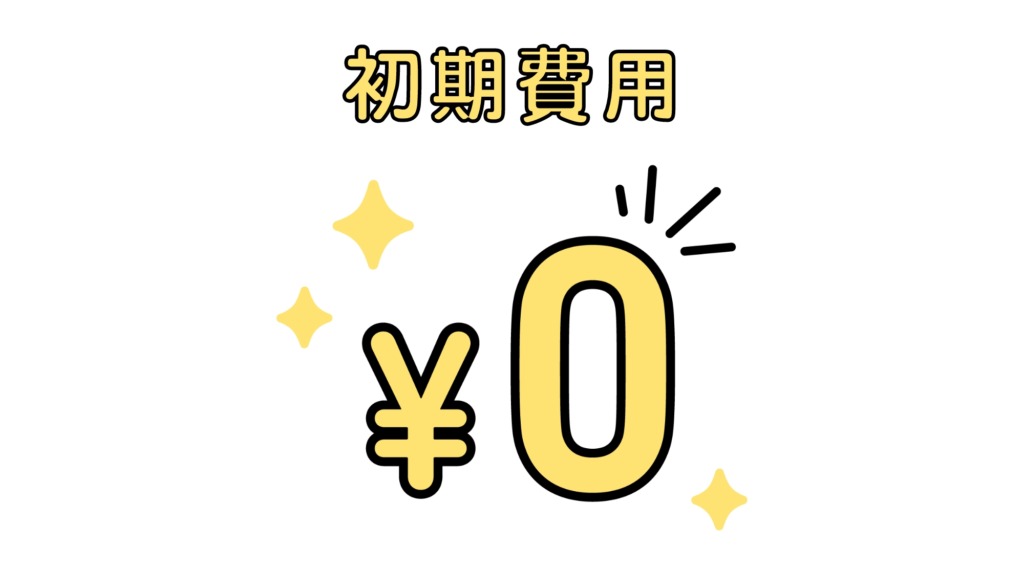
初期費用0円サービスの仕組みとは
多くの「初期費用0円」サービスは、初期の制作費を無料にして、その分を月額料金に分割して回収する仕組みです。
つまり、完全に“無料で作ってくれる”わけではありません。
たとえば、通常30万円かかる制作費を「月1万円×30ヶ月」で支払うようなイメージです。
最初の負担が軽くなる代わりに、契約期間が長く設定されていることが多いのが特徴です。
一般的な料金モデルの例
| プランタイプ | 初期費用 | 月額費用 | 契約期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 通常制作 | 30万円前後 | 0〜5,000円 | なし | 一括払いで所有権は自社に |
| 初期費用0円プラン | 0円 | 1万〜2万円 | 2〜3年 | 契約中はデータの所有権なしが多い |
| サブスクリプション型 | 0〜5万円 | 5,000〜1万円 | 継続契約 | CMS利用料込み・更新サポートあり |
見た目の費用だけでなく、「契約期間」「解約条件」「データの扱い」を必ず確認しておくことが重要です。
メリット:初期負担が少なく導入しやすい
初期費用0円サービスの最大の魅力は、すぐにホームページを持てることです。
まとまった予算を確保できない個人事業主や創業直後の企業にとっては、大きなメリットです。
また、ドメイン取得やサーバー設定、デザインテンプレートの準備などを代行してくれるため、
専門知識がなくても簡単に始められる点も人気の理由です。
初期費用0円のホームページ制作サービスは本当にお得?
初期費用0円のサービスには魅力的な面もありますが、注意すべきポイントもいくつか存在します。
特に、長期契約やデータの扱いなどを理解せずに契約してしまうと、後から後悔するケースもあります。
ここでは、利用前に知っておきたい注意点と、賢く活用するためのポイントを紹介します。
注意点① 契約期間中は解約できない場合がある
多くの0円プランでは、2〜3年の契約期間が設定されています。
この期間中に解約しようとすると、残りの月額料金を一括請求されることがあります。
つまり、実質的には「分割払い」で制作費を支払っているのと同じ仕組みです。
短期間でリニューアルを検討している場合や、事業内容が変わる可能性がある場合は注意が必要です。
注意点② ホームページの“所有権”が自社にないケースがある
契約期間中、ホームページのデータ(文章・画像・デザインなど)の著作権や管理権が制作会社にあるケースもあります。
この場合、解約するとデータを引き継げず、サイトが消えてしまうことがあります。
特に、「データの譲渡は不可」「契約終了後は削除」といった規約は要チェックです。
自社の資産として長く使いたい場合は、データを自社で管理できるかどうかを必ず確認しましょう。
注意点③ テンプレート制で自由度が低い
多くの初期費用0円サービスは、既存テンプレートを使って短期間で制作します。
そのため、デザインや機能のカスタマイズが制限されていることが多いです。
「とりあえず名刺代わりのサイトがほしい」場合には十分ですが、
ブランディングやSEOに力を入れたい企業には、機能面で物足りなく感じる可能性があります。
注意点④ 月額費が積み重なると割高になる
一見安く見える月額料金も、長期的に支払うと総額は高くなります。
たとえば、
- 月額1.5万円 × 36ヶ月 = 54万円
となり、通常の制作会社に依頼するよりも高額になるケースもあります。
初期費用0円は「支払いのタイミングを後ろにずらしただけ」と考えるのが正確です。
賢く使うためのポイント
とはいえ、初期費用0円サービスがすべて悪いわけではありません。
以下のようなケースでは、むしろ有効に活用できます。
- 起業したばかりで初期費用を抑えたい
- まずは小規模なサイトを持ってみたい
- 契約期間後にデータを引き継げるプランを選べる
契約前に必ず「契約期間」「解約条件」「データの取り扱い」を確認し、
“お試し用”か“本格運用”かを明確に使い分けることが大切です。
まとめ:初期費用0円=リスク0円ではない
初期費用0円は、導入のハードルを下げてくれる便利な仕組みですが、
契約内容をよく確認せずに利用すると、長期的には不利になることもあります。
「短期で試す」「資金繰りを優先する」といった明確な目的をもって使うなら、有効な選択肢です。
一方で、将来的に拡張や運用を考えている場合は、最初から通常の制作プランを選んだほうが結果的に安く済むこともあります。
ホームページ費用の見積もりを比較するときの注意点
ホームページを依頼するとき、多くの人が複数の制作会社やフリーランスに見積もりを依頼します。
しかし、「同じ条件で依頼したのに、金額が全然違う…」という経験をした方も多いのではないでしょうか。
実は、見積もりの金額差には明確な理由があります。
見た目の金額だけで判断してしまうと、後から「思ったより高くついた」「対応してもらえなかった」と後悔することもあります。
ここでは、見積もりを比較するときに必ず確認しておくべきポイントを紹介します。

ポイント① 「作業範囲」が同じ条件になっているか確認する
見積もりの金額が異なる最大の理由は、作業範囲の違いです。
たとえば、同じ「10ページのサイト」でも、以下のような項目が含まれるかどうかで金額は大きく変わります。
- 原稿作成や画像加工は含まれているか
- スマートフォン対応(レスポンシブ対応)は含まれるか
- SEO設定やGoogle連携設定はどこまで行うか
見積もりを比較する前に、「各社がどこまで対応してくれるのか」を一覧にして整理しておくと、内容の違いが一目でわかります。
ポイント② 「デザイン費」と「機能実装費」を分けて見る
「デザインのクオリティ」と「サイトの機能」は別の費用項目です。
見積書で「一式」とだけ書かれている場合、どこにどれだけ費用がかかっているのか分かりにくいことがあります。
理想的なのは、以下のように項目ごとに明確に分かれている見積もりです。
| 項目 | 内容 | 費用目安 |
|---|---|---|
| デザイン費 | トップ・下層ページのデザイン制作 | 10〜20万円 |
| コーディング費 | HTML/CSSの実装 | 10万円前後 |
| 機能実装費 | 問い合わせフォーム・CMS設定など | 5〜15万円 |
| ライティング費 | 原稿作成・構成 | 3〜10万円 |
このように内訳を見れば、どの部分にコストがかかっているのかが明確になります。
特に中小企業では、デザインよりも機能性や運用サポートを重視するケースが多く、
費用のかけ方を目的に合わせて見直すことが大切です。
ポイント③ 「納品後のサポート体制」があるか
制作が終わったあとも、ホームページには更新や修正が欠かせません。
そのため、納品後の対応範囲を確認しておくことは非常に重要です。
たとえば、以下のようなサポート内容を確認しておきましょう。
- 修正対応は納品後どれくらいまで無料か
- 更新作業の依頼方法や費用はどうなっているか
- 不具合が起きた場合の対応スピードは早いか
安い見積もりの中には、納品後のサポートが一切含まれていない場合もあります。
短期的なコストよりも、長期的に安心して運用できるかを基準に判断しましょう。
ポイント④ 担当者とのコミュニケーションが取りやすいか
制作会社やフリーランスを選ぶうえで、担当者との相性も大切です。
どれだけ安くても、こちらの要望を理解してくれない相手では、結果的に時間とコストが無駄になります。
打ち合わせ時の対応を見て、以下のような点を確認しておくと安心です。
- 質問に対して丁寧に説明してくれるか
- 専門用語ばかりでなく、わかりやすい言葉で話してくれるか
- 要望に対して柔軟に提案してくれるか
「安心して任せられる」と感じられる担当者であれば、制作の進行もスムーズになり、結果的にトラブルを防ぐことができます。
ポイント⑤ 異常に安い見積もりには注意
複数社から見積もりを取ると、1社だけ極端に安い金額を提示してくるケースがあります。
しかし、その裏には以下のようなリスクが隠れていることもあります。
- テンプレート流用で独自性がない
- 原稿や画像の用意がすべて依頼者任せ
- 納品後のサポートが一切なし
- 途中から追加費用が発生する
特に「一式◯万円」というシンプルな見積もりは、内容が不透明なことが多いため注意が必要です。
一見お得に見えても、結果的に修正費やリニューアル費がかさむケースは少なくありません。
まとめ:見積もり比較は「数字」ではなく「中身」で判断
見積もりを比較する際は、作業範囲・サポート体制・目的との整合性をセットで確認することが大切です。
最終的には、
「この会社なら任せられる」
「この金額なら納得できる」
という“納得感”が得られる見積もりを選ぶのが理想です。
ホームページリニューアルを成功させる鍵:RFP(提案依頼書)の作成
ホームページのリニューアルを成功させるには、制作会社に「目的」や「要望」を正確に伝えることが大切です。
その際に役立つのが RFP(Request For Proposal/提案依頼書) です。
RFPを作成しておくことで、依頼内容の伝え漏れや認識のズレを防ぎ、スムーズにプロジェクトを進行できます。
RFP(提案依頼書)とは?
RFPとは、ホームページ制作会社に依頼する際に、リニューアルの目的や要件をまとめた文書です。
プロジェクトの方向性を明確にし、制作会社との認識を合わせるための「設計図」のような役割を持ちます。
RFPに入れておくべき主な項目
RFPの内容は企業ごとに異なりますが、基本的には次のような項目を押さえましょう。
- リニューアルの目的・背景(なぜ作り直すのか、現状の課題)
- 達成したい目標(KPI・KGI)(例:問い合わせ件数を2倍にする)
- ターゲットユーザー像(年齢・職業・関心など)
- スケジュール・予算の目安
- 実装したい機能や要件(CMS利用、スマホ対応など)
まとめ:費用だけでなく「目的」に合った依頼先を選ぼう
ホームページ制作の費用は、「依頼先」や「目的」によって大きく変わります。
安く抑えることも、しっかり投資して成果を出すことも、どちらも正解です。
大切なのは、自社がホームページで何を実現したいのかを明確にすることです。
ホームページの費用は「目的」と「手段」で決まる
たとえば、
- 名刺代わりのサイトなら、テンプレートを使って安くスピーディーに
- 集客を狙うサイトなら、SEOや広告に投資して長期的に育てる
- 採用目的のサイトなら、デザイン性や情報発信力を重視
このように、目的によって最適な依頼先や費用配分はまったく異なります。
「何のために作るのか」を最初に整理することで、無駄なコストをかけず、納得できるサイトを作ることができます。
費用の安さよりも「信頼」と「サポート」を重視
見積もり金額が安くても、納品後に対応が遅かったり、更新ができなければ意味がありません。
特に個人事業主や中小企業の場合、運用面のサポートがしっかりしている制作会社を選ぶことが、長期的な成功につながります。
ホームページは作って終わりではなく、運用して成果を出していくものです。
制作後のフォロー体制まで含めて比較・検討しましょう。
最後に:コストではなく“投資”として考える
ホームページ制作費は「支出」ではなく、未来への投資です。
見込み客が増えたり、信頼性が高まったりすることで、費用以上の成果を生み出すことができます。
短期的な安さではなく、長期的な価値を見据えて依頼先を選ぶこと。
それが、結果として“コスパの良いホームページ”を実現する最も確実な方法です。
この記事を通じて、ホームページの費用構造や相場感が明確になり、
自社に最適な制作プランを選ぶためのヒントになれば幸いです。

- 監修者
- 田邉 文章 Fumiaki Tanabe
